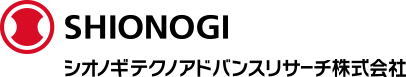研究技術職(薬理評価)
職種:研究技術職_薬理評価
入社:2022年度新卒
出身:理学研究科 生物科学専攻
仕事内容
『ハイスループットなin vitro薬効評価』
私は、疾患領域を問わず、創薬初期の探索研究から前臨床試験に至るまでのin vitro薬効評価業務を担当しています。低分子創薬では、標的タンパク質(酵素等)や動物由来の細胞を用いて、化合物の結合活性、酵素阻害活性、機能活性を評価しています。ワクチン開発では、ワクチン投与検体を用いた各種試験を通して、免疫原性を評価しています。自動分注機やロボットシステムを駆使し、多数の化合物や検体を短期間でハイスループットに評価することで、構造活性相関(SAR:Structure-activity Relationships)研究の加速に寄与しています。また、新規標的に対して既存の評価系が適用できない場合には、目的に応じて新たな評価系の構築も行っています。このように、in vitro薬効評価を継続的に積み重ねることで、高い薬効を示す化合物や有望なワクチン候補の創出に貢献しています。
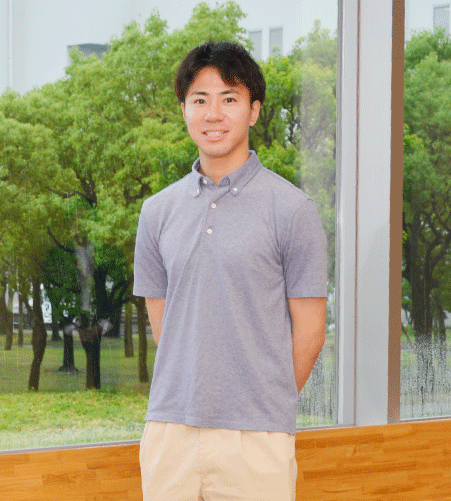
やりがい/うれしかったエピソード
『自動解析システム構築による貢献』
業務に付加価値を加えられたと実感できた時に、大きなやりがいを感じます。具体的には、「評価系の改善によるスループットの向上」、「新規導入した自動分注機の活用によるタスクの軽減」、「自動解析システムの構築による早期のデータ提供」などが挙げられます。特に、3点目の自動解析システムの構築では、社外講座の受講や塩野義製薬研究員との連携を通じて、Pythonを用いた解析システムを開発しました。この取り組みにより、データの速報性が大きく向上し、ケミストのニーズであった納期短縮を実現することができました。また、この成果が評価され、年に1回実施されるSTAR社長賞の「皆で選ぶ社長賞」部門において「チャレンジSTAR賞」を受賞しました。こうした社内からのフィードバックは大きな励みとなっています。このように、STARでは挑戦しやすい風土が根付いており、新たなことに取り組みながら創薬への貢献を実感しています。
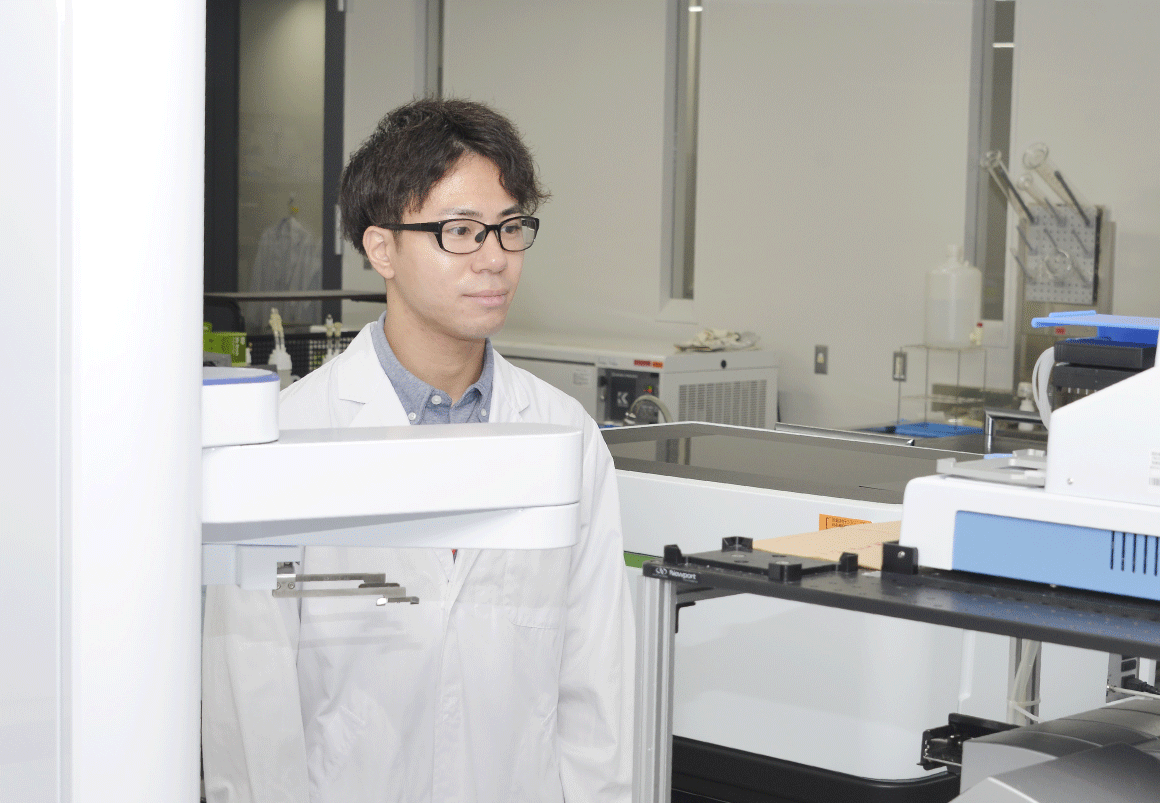
入社した理由
『実験技術で患者さんに貢献したい』
大学の研究室では、新しい実験に挑戦する楽しさや、初めて得られたデータを確認する瞬間の高揚感を感じながら、研究に没頭していました。一方で、自身の研究成果が患者さんに届くまでには長い道のりがあることを痛感し、「より社会貢献を実感できる環境で研究に携わりたい」と考えるようになりました。就職活動では、多様な研究テーマに関われる環境、上市品に携われる可能性の高さ、実験に専念できる体制、そしてSHIONOGIの創薬比率の高さに魅力を感じ、実験技術で患者さんの健康に貢献できるSTARに強く惹かれました。また、学生時代にコロナ禍を経験し、感染症に対する治療薬やワクチンの創出が経済安全保障にもつながる重要な取り組みであることを実感し、感染症研究に注力するSHIONOGIグループで働きたいという思いが一層強まりました。

私のとある1日
6:30 起床
8:00 出社・メールチェック・業務予定の確認
自転車でストレスなく通勤しています。
出社時は自分だけでなく一緒に働く派遣社員さんの予定を確認し、時にはサポートしています。
8:30 実験① サンプル調製・ロボットシステムの準備
384ウェルプレートへのサンプル添加~測定を自動化しているロボットシステムを活用し、ワクチンの免疫原性評価を実施しています。
10:00 実験② 遺伝子導入細胞を用いた実験
ロボットシステムに実験を任せている間、低分子化合物の機能活性を評価するため、細胞を用いた実験を実施します。
12:00 昼食・休憩
実験の予定に合わせて、11:20~14:00の間に社内食堂で昼食をとっています。
13:00 実験② 測定・データ解析
反応が完了したらマイクロプレートリーダーで測定し、データを解析します。
15:00 翌日の準備
翌日の実験に備え、電子実験ノートの準備や実験の前処置を実施します。
16:00 細胞の継代
実験に使用している細胞を維持するため、継代します。
16:30 実験① 測定・ロボットシステムの片付け
ロボットシステムによる測定完了後、機器の洗浄や廃液の処理を行います。
17:00 退社
迅速なデータ報告が求められる場合やロボットシステムを夜間に運転する場合は、勤務時間を調整して対応します。
帰りも自転車で気分をリフレッシュします。時間があるときは近所の坂を走ったり、ジムで筋トレしたりしています。また、業務で活用しているPythonの勉強に励んでいます。