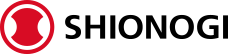「日経・FT感染症会議」は、国内外の企業、行政機関・団体、アカデミアなどすべてのステークホルダーが一堂に集まる国際会議です。第12回を迎えた25年は、米国の世界保健機関(WHO)脱退表明など世界の分断が進むなか、「分断の時代に求められる新たな価値観は?」をテーマに、日本が果たすべき役割などが議論されました。
当社手代木および澤田が登壇した演題は以下の通りです。
10月7日(火):澤田登壇
· 議題1:国際連携 ~グローバルヘルス・セキュリティーの向上を目指して~
· 議題2:イノベーション ~研究開発と対策を加速化するために~
· 特別セッション4:AMR対策において重要な創薬研究活動の強化
10月8日(水):手代木登壇
· 議題3:資源の戦略的投入 ~新たなる危機への備えのために~
当社代表取締役会長兼社長CEO 手代木 功は、以下のように述べています。
「感染症対策を強化するためには、産官学が連携し、平時から持続的に研究開発や供給体制の整備、人材育成などを支える包括的な仕組みを構築することが重要です。特に日本では、制度のさらなる整備や支援のスピード・規模の拡充が求められます。また、グローバルな感染症危機に対応するためには、国際連携を一層推進し、日本の役割を積極的に発揮していくことが不可欠です。」
当社手代木と澤田が登壇したプレゼンテーションの講演要旨は、別紙をご参照ください。
塩野義製薬は、取り組むべきマテリアリティ(重要課題)として「感染症の脅威からの解放」および「医療アクセスの向上」を特定し、感染症のトータルケアの実現に向けて、国内外のパートナーも含めた連携活動を推進しています。当社は引き続き、感染症のリーディングカンパニーとして、公衆衛生上の大きな課題であるAMRやCOVID-19など幅広い感染症への対策に継続して取り組んでまいります。
以 上
[お問合せ先]
塩野義製薬ウェブサイト お問い合わせフォーム:https://www.shionogi.com/jp/ja/quest.html#3.
別紙
以下は、手代木および澤田の発表内容の講演要旨です。
【講演要旨】
議題3:資源の戦略的投入 ~新たなる危機への備えのために~
新たなパンデミックに備えた平時からの取り組みの重要性
新たなパンデミックに備える必要性について、反対される方はいないと思います。しかし、実際に準備が進んでいるかというと、企業としては心もとない状況です。ショッキングな事実として、世界を壊すほどのパンデミックを経験したにもかかわらず、感染症を専門とする企業はベンチャーを含めて激減しています。さらに、医学部で感染症を専門にしたいという学生も増えておらず、むしろ減少傾向にあります。人命だけでなく社会をも破壊する感染症の重大性は理解されているはずですが、現状を見ると「忘れたい」「なかったことにしたい」という雰囲気が広がっています。
感染症領域のビジネスモデルの課題
2022~2023年には、欧米大手を含め感染症対応で成功した企業は一定の財務的リワードを得ました。しかし、2024~2025年と需要が減少するにつれ、財務的リワードが減少し、株主・投資家からの批判が強まり、「感染症事業はやめるべき」という明確なメッセージが出ています。この状況を変えるには、サステイナブルなビジネスモデルの構築が不可欠です。そうでなければ、次のパンデミックに対応できません。
民間企業としての取り組み:アジアIDシンポジウム
私たちは座して待つわけにはいきません。そこで昨年から、企業色を排した場の提供として「アジアIDシンポジウム」を開催しています。アジア各国の基幹病院で感染症に携わる専門家、日本では国立健康危機管理研究機構(JIHS)や厚生労働省の方々にも参加いただき、経験や知見の共有、継続的なネットワーキングを進めています。産官学が継続的に議論できる仕組みは、アジア全体でまだ十分に存在していません。今後、こうした場を強化していく必要があります。
次の感染症に備えた治療薬・予防薬の開発に対する米国の支援
私たちは次の新型コロナ感染症の対策に向け、治療薬を予防に活用できないかという取り組みを進めています。米国はこうした取り組みに対して非常に迅速かつ大規模に対応し、継続的な支援を行っています。成功時の買い取りや備蓄も含めた包括的な仕組みがあり、企業としても踏み込みやすい環境です。その結果、米国への優先的な供給を考えざるを得ない状況が生まれています。さらに、米国政府は生産設備への大規模支援を計画しており、当社も申請中です。こうした仕組みを日本でどこまで構築できるかが、今後の重要なテーマです。
日本政府の取り組みと今後の課題
政府も抗菌薬確保支援事業やワクチン大規模臨床試験支援事業など、治療薬・診断薬への支援を拡大しています。しかし、研究開発から成功時のリワードまで、感染症を「保険的な投資」として捉えなければ、企業は動けません。私はこれを「消火器モデル」と呼んでいます。一家に一台ある消火器を使わなかったからといって悔しがる人はいませんが、いざという時に使えるようにするためには、年間一定の費用を払い続ける必要があります。国全体でその仕組みを整えなければなりません。
創薬研究の指針については、国による要件定義が進んでいることは非常に心強いです。米国BARDA(生物医学先端研究開発局)が危機対応医薬品のターゲットプロダクトプロファイルを策定しているように、こうした情報を共有し、アカデミアも含めて求められる方向性を議論することが重要です。方向性としては進んでいますが、スピードと規模の面では、まだまだ取り組みを加速する必要があります。
グローバルヘルスにおける日本の役割
たまたまビル・ゲイツ氏が来日した際に話したのですが、日本のグローバルヘルスにおける役割が今ほど求められている時はないと明言されています。米国や欧州、中国で自国主義が進展する中、アフリカを含め日本への期待は非常に大きい状況です。だからこそ、産官学が連携し、国としての仕組みをどう構築するかを議論していく必要があります。
特別セッション4:AMR対策において重要な創薬研究活動の強化
多剤耐性菌感染症の危機と新規抗菌薬創製の課題
若手研究者が感染症領域に参入できていない現状がありますが、その中でも特に深刻なのが、細菌感染症、特に多剤耐性菌感染症の領域です。
抗菌薬は、必要な患者にのみ使用することが求められる特殊な領域です。多剤耐性菌に効く薬は通常の感染症にも効果を持つ場合が多いですが、乱用を防ぐため、一般感染症には使えません。その結果、販売量を増やすことを目的にできず、市場は縮小し、不確実性が高まります。市場の魅力が低下することで、大手企業は撤退し、研究者も参入しなくなり、研究開発力が低下します。こうして新規抗菌薬が生まれない一方で、耐性菌は必ず発生するという負のサイクルが続いています。これは、極めて危機的な状況です。
米国市場の現状とスタートアップの苦境
通常、米国は最も魅力的な市場とされ、スタートアップもまず米国での展開を目指します。しかし、感染症領域では、FDAによる承認を得て上市しても、破産や売上不振に陥る企業が続出しています。実際、5社のスタートアップで総額23億ドルの損失が発生しました。BARDAなどから多額の投資が行われても、結果的に損失となり、持続的成長や投資継続は困難な状況です。
大手企業撤退と研究者流出
大手製薬企業の撤退により、抗菌薬研究開発を放棄した6社の研究者の動向を調査したところ、1回目の転職で約20%しかこの領域に残らず、2回目では10%程度に減少しています。
アカデミアにおいても研究は減少傾向で、論文数・著者数ともに減少しています。WHOの報告によると、2023年時点で臨床開発段階の化合物は97件、2025年には90件に減少。新規メカニズムを持つ化合物はわずか15件にとどまり、イノベーションの欠如が顕著です。
AMR対策における課題
創薬研究を活性化するためには、複数の深刻な課題があります。まず、基礎研究・前臨床段階では、新規研究者の参画が見込めず、イノベーションが起きにくい環境が続いています。加えて、資金不足も深刻で、研究の進展を阻む大きな要因となっています。次に、臨床試験段階では、多剤耐性菌感染症のグローバル試験が極めて困難です。実際、弊社が実施した試験では、2,000例をスクリーニングしても、臨床試験に登録できたのはわずか1例という厳しい現実があります。試験デザインや規制対応に加え、コストが高く、市場性や成功確率が低いことも大きな課題です。さらに、上市後の課題として、低中所得国への供給には製造技術の移転、低温保存、供給チェーンの整備が不可欠です。加えて、適正使用を確保するためには、ヘルスシステムの構築や国別ガイドラインの策定が必要です。薬剤感受性のサーベイランスも重要であり、こうした体制を整えるには膨大なリソースが求められます。このように、創薬から上市後まで、AMR対策には多層的な課題が存在し、薬剤発売後も継続的な取り組みが不可欠です。
創薬エコシステムを動かすために
感染症領域の創薬エコシステムを維持・強化するためには、プル型とプッシュ型の両方のインセンティブが不可欠です。まず、プッシュ型インセンティブは研究開発を後押しする仕組みであり、代表例としてAMRアクションファンドによる後期臨床試験支援があります。こうした取り組みは、創薬の初期から臨床試験までを支える重要な役割を果たしています。一方で、プル型インセンティブは上市後の持続可能性を確保する仕組みですが、現状では十分に整備されておらず、今後の議論が必要です。プル型の仕組みがなければ、企業は長期的な投資を継続できず、創薬エコシステム全体が停滞する恐れがあります。弊社としても、プッシュ型インセンティブの一環として、INCATEとのコラボレーションを進めています。こうした取り組みを通じて、研究開発の活性化と持続可能なビジネスモデルの構築を目指しています。