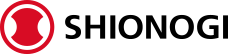環境に含まれるDNAから未来を予測する
~公衆衛生と地球の健康に貢献するAdvanSentinel~

海外ではインフラとして活用されている下水サーベイランス
―「下水サーベイランス」とは、どのような技術ですか?
―下水サーベイランスの利点を教えてください。
―そのような利点を持つ下水サーベイランスですが、海外でも行われているのでしょうか?
アメリカではCDC(疾病予防管理センター)が主導して、約1,200~1,600カ所(全国の人口の約50%をカバー)で下水疫学調査が実施されており、政府のダッシュボードでデータが公開されるなど、社会インフラとしての導入が進んでいます。
EUでは、複数のウイルスと変異株をモニタリングするための下水疫学調査が義務化され、2026年までに全加盟国が下水疫学調査を導入することが必須とされています。

しかし、あのひっ迫したパンデミックの日々を思い起こしてみてください。あのとき、もし下水が異変を知らせてくれたら? そう考えると、下水サーベイランスの重要性や有用性が、より身近に感じられるのではないでしょうか。
検出感度を100倍高めたCOPMAN法
―AdvanSentinelが設立された背景は?
―岩本さんお一人で始められたプロジェクトだったのですか、詳しく教えてください。
岩本:2017年に新卒で塩野義製薬に入社し、デジタルトランスフォーメーション(DX)を推進する部署に配属となりました。塩野義製薬の強みである感染症でDXが活用できないかとリサーチしてみると、感染症は社会へのインパクトが大きい割に、いままでの対策は薬やワクチンという個人単位での対策がメインでした。
社会における感染コントロールという視点なら、個人対策よりも社会全体に対する感染症モニタリングのほうが重要で、より効率的ではと考えました。2019年の第1回新規事業の社内公募「やりたいねん!」で下水サーベイランス事業を提案、50件ほどの候補の中から受賞して本プロジェクトを始めるに至りました。
―岩本さんのアイデアが、社内コンペで見事採択されたのですね。
岩本:スタート当時は私と公募で来ていただいた方の2人で、本来の業務と並行しながら下水サーベイランス事業を準備していたところ、次第に新型コロナウイルス感染が国内にも広がっていきます。「今こそ社会に必要な技術では」と事業開始の加速を決意しました。
下水中のコロナウイルス動向について、すばらしい論文を発表されていた北島正章先生(当時北海道大学准教授、現東京大学特任教授)に共同研究を申し出て、検出感度を向上させる技術を確立しました。PCRをかける前に阻害するゴミなどをフィルターで除去していましたが、実はフィルターで除去される固形物に高濃度のウイルスが付着していたと判明。加えて、PCRをかける前に予備的に増幅(プレアンプリフィケーション)させておくと、さらに効率よく検出できることが分かり、プロトコル(実験手順)を最適化していきました。結果として、高額な機器を使わずに100倍ほど感度を向上させたEPISENS*法を開発しました。その後、塩野義製薬の研究所が中心となり、高感度かつ自動化可能なCOPMAN法**の開発に成功しました。
*EPISENS :Efficient and Practical virus Identification System with ENhanced Sensitivity
**COPMAN:Coagulation and Proteolysis method using Magnetic beads for detection of Nucleic acids in wastewater
―COPMAN法は、コストをかけずに感度を約100倍も高められたのですね。その後、島津製作所との合弁会社設立にまで至った経緯をお聞かせください。
地域住民の健康と医療リソースを守る下水サーベイランス

―AdvanSentinelの事業は下水にとどまらず、環境をひろく調査できると伺いました。
- 1下水サーベイランス:下水中に含まれる感染症の原因となる微生物やウイルスの遺伝子を測定し、地域全体の感染状況を把握する疫学調査
- 2鳥インフルエンザ・湖沼水モニタリング:湖水などから鳥インフルエンザウイルスを早期に検出
- 3環境DNAモニタリング:環境中のDNAから生物の種類や量を特定し、生物多様性の評価に貢献
―これまでに手がけられた、下水サーベイランスの具体的な事例をお聞かせください。
岩本:新型コロナウイルス感染症が感染症法2類から5類に引き下げられた2023年5月、感染者の全数把握が終了となりました。感染者数が分からないと、自治体としては感染対策のレベルを決める指標がなくなり、市民の感染対策の意識も薄れます。そこで、兵庫県養父市では全数検査に代わる指標として、下水サーベイランスを導入いただきました。
週に2回、市内5カ所で下水サンプリングによるウイルス量のモニタリングを実施。自治体はその結果を信号機モデル(青:収束期、黄:警戒期、赤:拡大期)で市民に分かりやすく伝えました。「最近また赤くなったね」「お互い気をつけないと」といった日常会話を通じて感染の気配を共有できるのは、不安感の解消や感染対策意識の高まりにつながります。
高齢化が進む地域において、限られた医療リソースと市民の健康を守る方法として、下水サーベイランスは低コストながら非常に有効な手段といえます。

環境DNAモニタリングで地球の健康「プラネタリー・ヘルス」を守る
―全数検査のように巨額の費用をかけなくても感染動向が分かるのはすばらしいですね。鳥インフルエンザ・湖沼水モニタリングについても、社会的意義や具体例を教えてください。
岩本:大切に育てた鶏が何千万羽も殺処分され、廃業も余儀なくされる鳥インフルエンザは、養鶏農家や関係者の精神的・費用的な負担が非常に大きい問題です。AdvanSentinelは、ウイルス量が希薄なため検出が困難だった湖水から、鳥インフルエンザウイルスの安定的な検出に成功しました。
宮崎県での調査では、鶏舎での鳥インフルエンザ発生の1〜6週間前に近隣湖水から先行してウイルスが検出され、予報として活用できる可能性が示されました。養鶏農家の方が感染が出た瞬間にすべてを失う恐怖と常に向き合い続けるのは、並大抵のことではありません。モニタリングによって必要なときのみ厳重な対策を取れるようになり、漠然とした緊張状態から養鶏農家を解放します。
―もう一つの柱である環境DNAモニタリングとは、どのようなサービスでしょうか?
岩本: 環境DNAモニタリングは、環境中に存在する微量のDNAを同様に濃縮・検出して、含まれるDNAから生物多様性を定量的・経時的に評価します。従来は困難だった生物種の特定や、時間経過による生態系の変化の把握が可能です。
企業がTNFD*(自然関連財務情報開示タスクフォース)に対応するために、自社工場周辺の自然環境の変化を定量的に評価する、といった活用法が広がっています。グラングリーン大阪(大阪市)や塩野義製薬が有する油日(あぶらひ)植物園(滋賀県甲賀市)では実証実験が進行中です。
*TNFD:自然資本への依存度と生態系への影響を評価し、これらの情報を企業や金融機関が投資家や他の利害関係者に提供するための枠組み。
―下水、湖沼、土壌、大気など、環境に含まれるDNAはこれまで想像していた以上の情報が含まれているのですね。AdvanSentinelが描く未来の展望についてお聞かせください。
岩本:まずは日本全体で200地点の下水サンプリングを目指しています。200は全国の政令指定都市+県庁所在地の数にあたり、人口の50%を網羅できる数です。そして島津製作所との協業を通じて、解析のブレを減らし地点ごとの比較ができるように、検査拠点の設立や自動化ラインの実装も進めています。
抗菌薬の適正使用のために、下水中の薬剤耐性菌が減少したら金銭的インセンティブを付与するなど、経済性に訴えて自助努力が機能する手法も考案中です。従来検出が困難とされた病原体だけでなく、未知の病原体も検出可能になってきていますし、バイオテロ対策といった国防的な用途にも下水サーベイランスが非常に役立つと考えています。
下水サーベイランスや環境DNAモニタリング技術の延長線上に、DNAの量や種類をリアルタイムで把握し、解析できるような未来を構想しています。いろいろ考えるのが好きで、頭の中にはアイデアの種がたくさん芽吹いていますが、やりたいことの1%も実現できていません。AdvanSentinelの取り組みが「プラネタリー・ヘルス(地球の健康)」に貢献することを目指して、新しい挑戦をしていきます。