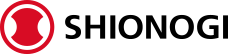IT負債をつくらない―現場に根付くDXの設計図

臨床心理学で得た「人へのケア」をIT業界で活かす

――学生時代は、今とはまったく異なる分野である臨床心理学を専攻されていたそうですね。そこから最初にIT業界を選ばれたのは、どのような経緯だったのでしょう。
林田進吾さん(以下、林田):臨床心理学に関心を持ったのは、高校時代に高齢者施設でボランティアを経験したことがきっかけです。身体的なケアだけでなく精神的なケアができてこそ、本当の幸せになれるのではないかと感じたからです。
とはいえ、大学時代は自分が何をしたいのか明確でなくて、就職については6歳上の兄がIT分野にいたことから「大変そうだけど楽しそう」と、軽い気持ちでした(笑)。
――社会人になってから、ITの現場ではどんな課題を感じてこられましたか。
林田:最初の職場は、1980年代に作られた古いシステムを改修しながら使い続ける環境でした。入力が複雑で、人の手が必要な作業も多く、現場の負担が大きかった。いわば「人がシステムに振り回されている」状況でした。その経験から「人が使いやすい仕組みをどう作るか」こそITの本質だと考えるようになりました。この「人に寄り添う設計」こそ、いま取り組んでいるIT負債をつくらないDXの出発点になっています。
転職を経て、今は塩野義製薬で、人事や経理財務、法務などコーポレート部門を支えるDXを進めています。目指しているのは、システムを入れ替えることそのものではなく、現場と対話しながら最も自然に機能する形を見つけていくDXです。心理学で学んだ「人を観察し、理解する姿勢」が、いまの仕事の根底にあると感じています。
現場に根づくDXとは――「負債をつくらない」設計思想

――林田さんにとって、DXとは何でしょう。
林田:私にとってDXは、単に技術を導入することではなく、デジタル(D)の力で組織を変革(X)し、長い目で見て実りをもたらす取り組みです。システムの導入ありきではなく、ITの観点から組織の全体最適を考え「その導入は正しいのか」を問い続けながら社内の人々の働きをサポートしています。
具体的に言えば、大きなテーマとなっているのは「IT負債」。せっかく導入してもうまく活用されないままになってしまうーーそうしたIT運用の課題を生まれないようにすることです。それが、持続的に成長できるDXの基盤になると考えています。
――「IT負債」について、詳しく教えてください。
林田:大企業が抱えがちな「不要なコストを生み出すIT」です。主に二つあり、ひとつは品質の低いシステムが導入されてしまうこと。要件通りに動かなければ、リカバリーに大きなコストが発生します。もうひとつは、機能が重複したシステムが複数存在してしまうこと。個別には充実しているようでも全体として無駄が多く、管理コストが膨れてしまいます。システム導入時に精査して、持続可能なシステム運用へと導くことが私の業務です。
IT専門のカウンセラーとして、現場に伴走する

――各部門の要望を調整するのはかなり大変そうです。理解を得られるよう工夫していることは?
林田:「この製品を入れたい」という要望には、まず目的や背景、理由などをITの専門的な観点から詳しく聞き出します。「この製品は他と比べてどんな優劣があるか」「投資回収は見合うか」などの質問を投げかけ、聞き役に徹して、業務の何をどのようにしていきたいのかを部門の人達自身にじっくり考えてもらいます。
――まるでITのカウンセリングですね。
林田:システムは、あくまで組織運営のためのツール。できるだけ相手に話してもらいやすい雰囲気を作り、「何をしたいのか」自身で答えを見つけてもらうように心がけています。先日、上司から「林田さんはホスピタリティがあるね」と言葉をかけられて本当に嬉しかったんです。大切にしている「人のために」という価値観を、ちゃんと見てもらえていると感じた言葉でした。
こうした取り組みがうまく進むのは、塩野義製薬に部署を超えて話しやすい雰囲気があるからだと思います。全社で力を合わせて目標を成し遂げようという意識が根付いていて、IT部門もその一員として動いています。キャリア採用のメンバーも多いですが、みな仲が良く社員の距離が近い環境です。上司も気さくに話を聞いてくれて何でも話しやすく、良い関係が築けています。
――IT負債という課題に向き合う中で、これからのDXをどんな形にしていきたいと考えていますか。
林田:DXやITの領域は、いまや会社の経営の屋台骨になっています。私たちは、IT負債を生まないような環境を整えながら、現場の人が働きやすい仕組みづくりを進めています。時には「厳しいな」と思われることもありますが、それも現場をより良くしたい気持ちが同じだから。
立場や視点は違っても、目指しているのは同じ未来です。現場と経営のあいだに立つ私たちは、課題を一緒に見つけ、最適な解決策を探していく伴走者でありたい。現場を理解したITの仲間たちと共に、これからも「人を起点にした設計図」を描き続き、現場に根付くDXを進めていきます。