“患者に届く薬”を生み出す力──SHIONOGIが次世代へ託す挑戦のバトン

1. 「より優れた化合物」を目指し続けた──HIV治療薬「ドルテグラビル」の20年
.jpg)
―まずは約20年かけてHIV治療薬「ドルテグラビル」の創薬に成功した川筋さんに伺います。開発はどのように進められたのでしょうか。
HIVは変異が起こりやすく、耐性ウイルスが生じやすい治療が難しいウイルスです。既存の作用機序の薬剤では耐性ウイルス出現が課題となっていたため、新しい作用機序の薬が必要だと考えました。そこで、SHIONOGIではHIVが持つ第三の酵素であるインテグラーゼの阻害剤に目をつけました。
―開発する前から耐性について考えられていたのですね。けれども、インテグラーゼの構造や活性の評価方法そのものも未知だったのでは?
―手作業で5万個のスクリーニングですか!当時はまだヒット化合物スクリーニング(HTS:High-Throughput Screening)ロボットがなかったのですね。
―世界的な企業との共同研究につながったのですね。新たなインテグラーゼ阻害剤の開発は順調に進みましたか?
川筋:共同研究活動から見出され、SHIONOGIとしては2つ目の化合物(S/GSK364735)による挑戦では、ヒトでしっかり抗ウイルス効果を確認できました。しかし、既に他社は1日1回服用可能なインテグラーゼ阻害剤を開発しており、一方で、我々の化合物は1日2回の服用が必要なことや、耐性リスクの面でも優位性を打ち出せず、苦渋の決断で開発は再び中止となりました。さすがに青くなりましたが、どんなときも「よりいいものを作ろう」と常に上を目指すのが研究者です。実は並行して、さらに服薬しやすくて、なおかつ耐性ウイルスのリスクが低い化合物の探索をひそかに進めていて、3度目の臨床試験の可能性を信じていました。
その化合物こそがドルテグラビルでした。現在でも、全世界の多くの患者さんに利用されています。
―なぜあきらめることなく、抗HIV創薬の研究を20年も続けられたのでしょうか?
2. 計算科学が創薬を変えた──新型コロナウイルス治療薬「エンシトレルビル」誕生の舞台裏

―続いて、新型コロナウイルス治療薬「エンシトレルビル」の創薬に携わった上原さんにお話を伺います。上原さんは、計算科学という新しいアプローチで創薬スピードの飛躍的な向上に貢献されました。
上原さん(以下、上原):通常、創薬には9〜16年ほどかかると言われています。一方、エンシトレルビルはわずか2年5カ月で国内緊急承認を取得しました。もちろん、必要なプロセスは省いていません。このスピードを可能にした一つの要因が、私の専門である計算科学です。バーチャルスクリーニングとは、一般的に数か月の期間を要するヒット化合物のスクリーニング(HTS:High-Throughput Screening)を、計算機シミュレーションによって高速に代替する手法です。エンシトレルビルの開発は、バーチャルスクリーニングを起点とした創薬が自社で初めて成功した、SHIONOGIの計算科学におけるひとつのターニングポイントとなりました。
川筋:SHIONOGIは黎明(れいめい)期から計算科学に積極的に取り組んできましたが、当時は全く実用レベルではありませんでした。それでもあきらめず技術を着実に積み重ねてきたことが、今回の成功につながったのだと思います。本人の努力に加え、挑戦を支える社風や技術革新が、困難な研究を前に進めました。
上原:まさにおっしゃるとおりで、先輩方が長年にわたって磨いてきた技術に加え、タンパク質の立体構造を正確に予測するAlphaFold2(2024年ノーベル化学賞受賞)の登場や、計算機の飛躍的な性能向上といった技術的なイノベーションが重なりました。多様な標的に対して、タンパク質と化合物の結合を高精度にシミュレーションできるようになりつつあり、計算科学が創薬に本格的に貢献できる時代が到来したと感じています。
―計算科学やシミュレーションと聞くと、ひたすらPCと向かい合っているイメージですが、実際はどのように業務を進めているのですか?
上原:私たち計算科学のメンバーは、「自分は計算科学者だから薬のことは分からない」と部屋にこもってデータだけを扱うのではなく、他部署のメンバーと話し合いながら業務を進めています。特に、ケミストとは同じ居室で仕事をしていることもあり、化合物のデザインや解析結果について日常的に議論をしています。多様な専門性を持つ人たちが、一つのチームとして研究を進めている点も成功につながったと思います。
川筋:部署の間に壁がなく、お互いに勉強し合う文化が根付いていることが、私たちがイノベーションを生み出せる秘訣(ひけつ)です。自主的に開催される勉強会で創薬全体を学ぶことができますから、学生時代の専攻を問わず、チーム全体が共通認識を持って創薬を進められます。

―人材育成が非常に手厚い印象を受けました。創薬への深い理解があったからこそ、シミュレーションの精度が高まり、成功を引き寄せたのですね。エンシトレルビルにつながるヒット化合物をどのように発見されたのか、詳しく教えてください。
上原:当時、感染症化学のグループ長だった立花裕樹さん主導のもと、ウイルス(SARS-CoV-2)の複製に重要な役割を果たす3CLプロテアーゼ(3CLpro)を標的とした阻害剤の探索に着手しました。3CLproの立体構造が COVID-19発生からわずか3カ月で解析・公開されていたこともあり、これまで技術を磨いてきた構造ベース創薬(SBDD)を進められる状況が整っていました。一刻を争う状況の中、少しでも開発スピードを高めるため、自社が保有するライブラリ化合物を対象にバーチャルスクリーニングを行い、ヒット候補の選抜を進めました。SHIONOGIでこれまでに合成された低分子化合物が蓄積された自社ライブラリの規模は数十万化合物に及びますが、わずか数日のバーチャルスクリーニングによって、阻害剤の候補を三百化合物まで絞り込むことができました。この中に、エンシトレルビルの種となるヒット化合物が含まれていたのです。
川筋:シミュレーション結果から、ヒット化合物と3CLproとの結合が非常にユニークで、「これは成功する」と直感したことを覚えています。本当にすごい技術に成長したなと感動しました。実は昔、このライブラリへの登録を推進したのは私たちでした。「自社で作った化合物は、必ず将来の財産になる」と信じて、合成した化合物を全て登録するようにルールを整備しました。2008年ごろだったでしょうか。本音を言うと、化合物を登録するという作業は本当に面倒な作業なのです。しかし、歴代のケミストたちが合成した化合物をコツコツと地道に登録し続けてくれたデータが「自社化合物ライブラリ」というかけがえのない財産となり、それがパンデミックという緊急時に役立ったと知ったときは本当に嬉しかったです。
上原:そうだったのですね!自社ライブラリから有望な化合物を見いだせたことで、チーム内の空気が一変しました。ヒット化合物は合成方法が確立された骨格を有しており、薬物動態や安全性に関るデータが豊富に蓄積されていたことも研究開発の大きなアドバンテージとなりました。
2022年11月、エンシトレルビルはCOVID-19治療薬として緊急承認を取得。本格的な研究開始からわずか2年5カ月で世の中に送り出すことができました。計算科学と自社ライブラリがなかったら、このスピードでは実現不可能だったでしょう。
3. 挑戦をつなぐ「バトンの継承」──自社創薬率69%を生む人と技術の連携

―創薬の成功率はわずか0.005%とも言われる狭き門です。そのなかでSHIONOGIの自社創薬率は69%、これは国内製薬企業の平均を大きく上回る水準です。この困難な道のりを乗り越え、新薬を生み出し続ける強さの源泉はどこにあるのでしょうか?
川筋: 感染症はインフルエンザや新型コロナウイルスなど、社会的に大きな影響を及ぼす疾患領域であり、決してなくなることのないテーマです。私はHIV治療薬の開発を通じて、患者さんが抱えるさまざまな苦しみに向き合ってきました。服薬のたびに「病気である」と認識させられる現実や、薬を見られて感染が知られる不安など、患者さんの声に耳を傾けることが、より良い治療法の実現につながります。現在は、そうした声に応える形で、抗HIV薬の長時間作用型注射剤の開発も進んでいます。患者さんによい薬を届けたいという想いこそが、私たちの研究の原動力です。
上原:「社会にとって不可欠な薬を届けたい」という強い思いに尽きます。エンシトレルビルの成功を足がかりに、私たち計算科学チームはより洗練されたバーチャルスクリーニング手法の確立を目指しています。ただし、それは一人では決して実現できません。優れた合成技術をもつケミストがいて、チームで支え合うからこそシミュレーションが現実になります。今後は、難聴や認知機能の低下といった生活の質(QOL)に関わる領域へも創薬を広げ、複雑な因果の網を読み解くために、計算科学の力をさらに発揮していきたいと考えています。
川筋:上原さんのような次の世代が、私たちの技術や志をしっかりと受け継ぎ、新たな領域へ挑んでいる姿を見ると、安心して未来を託せると感じます。創薬とは、想いと知恵を積み重ね、次代へと渡していく営みです。SHIONOGIの創薬力は、そうした“バトンの継承”によって、これからも深化していくのだと思います。

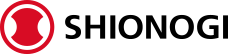
%20(1).png)