治療薬のない領域に挑む――創薬の力で「聞こえる未来」へ

高齢化が進むいま、世界で15億人以上が抱えるとされる「難聴」。自覚しづらく見過ごされがちな一方で、認知症や社会的孤立のリスクとの関連が指摘されるなど、社会的に見過ごせない課題になりつつあります。しかし、有効な治療薬はいまだ存在していません。塩野義製薬はこの課題に創薬力で挑むべく、Cilcare社(フランス)との共同研究を開始しました。
今回ご紹介するのは、難聴という新たな領域への挑戦と、「自分たちで治療薬を作りたい」という研究者たちの強い思い。塩野義製薬の新しい一歩をお届けします。
難聴という社会課題に、創薬で挑む
―加藤さんが取り組んでいる難聴とは、どのような疾患でしょうか。
―難聴の問題は、聞こえにくさだけですか?
さらに高齢者においては、難聴は認知症発症のリスク因子の一つとされています。難聴を改善することで認知症リスク低減につながる可能性も指摘されており、今後の研究が期待されています。

―それほど個人、そして社会全体に大きな影響があるのですね。高齢者が抱える聞こえづらさの原因と、難聴の治療法について教えてください。
加藤:実は、聴力は30-40歳代から加齢とともに少しずつ衰え始めるといわれています。非常に高い周波数の「モスキート音」は若者にしか聞こえない音として知られており、加齢による変化の一例です。さらに65歳を過ぎると聞こえにくさを感じる人が急激に増え、社会的な課題としても無視できない状況となっていきます。
有効な治療薬はいまだ存在せず、補聴器などの対症療法が中心です。いわゆる「アンメットメディカルニーズ」が極めて高い疾患の一つといえるでしょう。塩野義製薬では、「社会的影響度の高いQOL疾患」として、難聴創薬への挑戦を決意しました。
―塩野義製薬といえば感染症に強みを持つイメージです。聴覚領域への進出は大きなチャレンジだったのではないでしょうか?
Cilcare社と目指す新薬創出

―Cilcare社との協業で、どのような創薬を目指しているのですか?
加藤:一部の難聴では音の大きさは問題なく聞こえるのに、言葉や単語としてうまく伝わらないために、会話が成立しにくい症状がみられます。Cilcare社は、そういった特徴を持つ難聴の原因が、音を脳に伝達する神経経路の障害によるのではないかと推測して、聴覚神経の保護作用を持つ新しい治療薬候補「CIL001」を創出しました。
現在開発中のCIL001は聴覚神経を保護してシナプスの再結合を促進します。耳(鼓室)内に薬剤を直接注入することで、内耳にピンポイントで薬を届け、全身性の副作用を抑えられるのも特徴です。これまでの非臨床試験では、聴性脳幹反応(ABR)の改善やシナプス数の増加などの結果が得られています。
―内服とは異なる、ユニークな投薬法ですね。結果だけ聞くと順調そうですが、難聴領域における創薬の難しさを教えてください。
―現在開発中の化合物は「CIL001」の一つで、そちらのみに注力されているのですか?
「聞こえにくさ」を抱える人は、すぐ近くに存在している
―そもそも、難聴に対する創薬はどのように始まったのでしょうか?
その選択の背景には、社内で立ち上がったコミュニケーションバリアフリープロジェクトの存在も大きく影響しています。ここからは立ち上げメンバーの野口さんにバトンタッチします。

―では、ここからは野口さんにおうかがいします。野口さんが立ち上げられた「コミュニケーションバリアフリープロジェクト」とは、どのようなプロジェクトですか?
けれども、聴覚障がいの実態はほとんど知られておらず、「大きな声」で話しかけられがちです。私自身も先天性の聴覚障がいがあり、耳元でいきなり大きな声で話し掛けられびっくりしたことも(笑)。
―聴覚障がいがあっても聞こえる音もあり、必ずしも大きな声は必要ないのですね。初めて知りました。野口さんが経験された困りごとについて、詳しく教えていただけますか?
―なるほど、操作手順が分かれば問題なく進められるのに、コミュニケーション不足によって、まるで仕事ができないように思われてしまうのですね。
日本国内には聞こえない・聞こえにくい人が約2,000万人います。にもかかわらず、医療機関でのコミュニケーションバリアはまだ広く知られていません。何とかしなければ、と強く思いました。

―よい薬を作っても、正しく使われずに効果が発揮されない……。それは製薬企業としても早急にアクションが必要ですね。
「聞こえにくさ」への理解が、創薬の原動力に
―プロジェクトを通じて“聞こえにくさ”の課題が身近に感じられ、その理解が創薬にもつながっていったのですね
―最後に、今後の展望とメッセージをお願いいたします。
加藤:難聴は徐々に進行するため自覚しにくい疾患です。しかし、重症化する前に早期に治療へつなげることで、より良い結果につながる可能性があります。そのためにも、早期発見と早期治療の重要性を社会に発信し続けることが、私たちに課された使命だと感じています。
この治療薬が実用化されれば、世界中の難聴に悩む患者さんに希望を届けられるはずです。患者さんのQOL向上にも、大きく貢献できると信じています。ただ、薬の開発がゴールではありません。誰もが自分らしく、いきいきと暮らせる社会の実現こそが、私たちの目指す未来です。
新薬を世に送り出し、患者さんやご家族の「聞こえる未来」を創り、健やかで豊かな生活を送っていただけるよう、これからも誇りと情熱を持って未来の医療を創造し続けていきます。コミュニケーションバリアフリー活動と創薬の両輪で、社会の医療ニーズに応え続けたいと考えています。

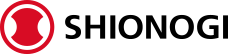

%20(1).png)