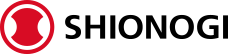挑むは誰ひとり取り残さない緩和ケア。コミュニケーションバリアフリーの実現をめざして
「痛みの日記帳」をご存じでしょうか?
この日記帳は、がん患者さんが痛みの状態や感じ方を記録し、医療従事者と共有することで、痛みの治療をサポートするツールです。
製薬会社がなぜ「痛みの日記帳」を作るのか疑問に思われるかもしれませんが、SHIONOGIは緩和ケア領域の研究開発や疾患啓発活動にも積極的に取り組んでおり、病気に悩む患者さんを支えることに注力しています。
その活動の一翼を担うのが緩和ケア領域のマーケティング部門です。同部門では、「誰ひとり取り残さない緩和ケア」「誰ひとり取り残さない疼痛治療」をめざして、患者さんの当たり前を支え、解のない難しい課題に挑み続けています。
緩和ケア領域のマーケティング部門の一員であり、「痛みの日記帳」の作成にも携わった山口康秀さんに、これまでの歩みを振り返っていただき、緩和ケアへの想いを伺いました。

がん患者と医療従事者の架け橋となる「痛みの日記帳」
──「痛みの日記帳」とはどのようなものか教えてください。
がんの痛みは、患者さん自身にしかわかりません。患者さんが痛みを正確に伝えることが、痛みの緩和につながります。しかし、痛みを言葉で表現することに支障があったり、痛みを我慢しなければならないと思っていたり、痛みを伝えても理解されないと感じている患者さんは少なくありません。そこで、痛みを正確に伝えられるためのツールとして、公益財団法人がん研究会有明病院緩和ケアセンター監修のもと「痛みの日記帳」を作成しました。

──確かに、痛みは主観的な感覚なので、それを言語化して医師や看護師に伝えるのは難しそうですね。
一言で痛みといっても、その痛みはどれくらい強いのか、どこが痛むのか、チクチクするのか、ズキズキするのかなど、種類はさまざまですので、できるだけ詳しく、ありのままを伝えなければいけません。そこで役立つのが「痛みの日記帳」です。
この日記帳は、痛みの強さ、質、部位、時間、影響、対処法などをイラストや記号で記録できるように工夫されています。医療スタッフは、患者さんが記入した日記帳の内容を参考に、患者さんに合った痛みの治療を検討することができます。
──なぜ、「痛みの日記帳」を作ろうと考えたのですか?
──患者さんの気持ちに寄り添いたいという想いで、緩和ケア領域に携わられているわけですね。
はい、そのとおりです。10年以上前、MR[i]としてがん専門病院を担当した際、医師、看護師、薬剤師の方々と痛みや苦痛についてお話しさせていただき、「人が苦しむとはどういうことなのか?」について自身の考えがいかに浅いものであったかを痛感しました。
体の痛みを緩和することはとても大事なことですが、それはがん患者さんが感じる痛みの一部にしかすぎません。医療用麻薬で体の痛みを和らげるだけでなく、心の痛みに寄り添うことも大切です。だからこそ、緩和ケアや医療麻薬に対する正しい理解の促進、患者さんやご家族、医療従事者との適切なコミュニケーションの推進は大きなテーマだと考えています。
[i] Medical Representative:医薬情報担当者
──緩和ケア領域において、新たな気づきを得たわけですね。
聴覚障がい患者が直面する情報格差解消への取り組み
──そんなときにコミュニケーションバリアフリープロジェクトと出会ったと伺っています。
まさにそのとおりです。コミュニケーションバリアフリープロジェクト(以下、CBF-PJ)は、「聴覚などに障がいのある患者さんが医薬品にアクセスする際のコミュニケーションの壁をなくす」ことをビジョンに掲げている社内横断プロジェクトです。音が聞き取りにくい、または聞こえない患者さんが直面する困難を取り除き、服薬指導の場で聞こえにくい・聞こえない患者さんに医薬品や医療に関する情報をお届けすることを目指しています

──「痛みの日記帳」とめざす方向性は同じようですね。
──聴覚障がいのあるがん患者さんは、どのようなことに困っているのでしょうか?
──具体的に、どのような取り組みをされているのでしょうか?
CBF-PJのメンバーとの交流から、がん患者さんの多様性に目を向け、「痛みの日記帳×CBF-PJ」の取り組みを始めました。このプロジェクトは始まったばかりで、現在は、どういった日記帳を作成するべきなのか、について議論している最中です。
「痛みの日記帳」を監修していただいた医療従事者からは、「日記帳を活用することで『痛みを医療者に伝えていい』『痛みの緩和の主役は患者自身』といったメッセージが伝わるきっかけになります。健聴者の方だけでなく、聴覚障がいのある方にも使いやすい資材を一緒に考えていきましょうとコメントをいただきました。
──CBF-PJリーダー塚本さんからのコメント
患者さんが治療を受けるうえで、医薬品に関する情報を知り、正しく理解することは極めて重要です。しかしながら、聴覚障がいのある方はしばしば、この情報を適切に取得できません。私たちは医療機関での情報格差をなくす、すなわち「コミュニケーションバリアを解消する」ことを目的に全社プロジェクトとして取り組んでいます。この想いは、がん治療や緩和ケアの領域であっても揺らぐことはありません。プロジェクトの究極のゴールは、障害の有無にかかわらず、すべての患者さんに正しい情報が行き届く世界を実現することであり、この世界の実現に向けて、常に患者さんファーストで山口さんとは今後も議論を重ねていきたいと思っています。
.jpg)
コミュニケーションギャップという言葉がなくなる日に向けて
──「痛みの日記帳」をさらに進化させていくわけですね。
はい。現状にとどまらずに前へ進むことで、より多くの困っている患者さんの役に立てるのではないかと考えています。
以前、がん看護専門看護師の方から、「がんのつらさは多くの要素が複雑に絡み合っている」と教えていただいたことがあります。従来は「身体の痛み」「精神的な痛み」、「がんによるつらさ」「がんとは関係のないつらさ」を分けて考えていましたが、それらが複合的に関係するという意識をもって、がん患者さんの多様性に目を向けることで、「誰ひとり取り残さない緩和ケア」と「誰ひとり取り残さないがん疼痛治療」の推進が重要だと気づかされました。

──「誰ひとり取り残さない緩和ケア」と「誰ひとり取り残さないがん疼痛治療」を推進するために、重要視していることや取り組んでいることはありますか?
CBF-PJと連携してシナジーを生み出すことで、外部環境に適し、DE&I[iii]の観点に立った「痛みの日記帳」を作りたいと考えています。現在は、社内関係者や医療従事者の方々からの声を聞きながら、日記帳そのものを改善するのがよいのか、ユニバーサルデザイン[iv]の要素を取り入れて新しいものを作成するのがよいのか、今の日記帳とは切り離して考えたほうがよいのか、議論を重ねているところです。
さまざまな人の意見やアイデアを取り入れて患者さんに寄り添った「痛みの日記帳」を作ることで、それが医療現場における「新しい当たり前」となり定着する。その当たり前となる種まきに力を注ぐことで、種が花を咲かせたときには、「誰ひとり取り残さない緩和ケア」「誰ひとり取り残さないがん疼痛治療」の実現につながると信じています。
[iii] Diversity Equity and Inclusion:多様性を認識する(ダイバーシティ)だけでなく、受け入れて、生かす(インクルージョン)こと。
[iv]「すべての人のためのデザイン」を意味し、年齢や障がいの有無などにかかわらず、最初からできるだけ多くの人が利用可能であるようにデザインすること