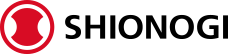数学の力で新薬開発をブースト。前例のないスピード解析
塩野義製薬の医薬開発本部解析センターに在籍するT.I.さん。2020年、コロナ禍に入社したT.I.さんは、入社2年目に、新型コロナウイルスの経口治療薬開発プロジェクトに解析担当として抜擢されます。
データ解析の最前線で何を考え、高い壁にどう挑んだのか。若きホープの言葉からは、塩野義製薬の社風と、解析の仕事がもつ奥深さが見えてきました。

社内一丸、「1日でも早く患者さまのもとへ」
ー数学科から製薬会社の統計解析の道を選んだきっかけを教えてください。
ー新型コロナウイルス治療薬開発では、前例のない迅速な解析に挑戦しました。

入社2年目のゴールデンウィーク頃に、上長から「新型コロナウイルスの治療薬の開発が動き出す。統計解析の実務担当を任せる。」と告げられました。
当時は新型コロナウイルス治療薬の選択肢が限られていて、1日でも早く患者さまに新薬を届けたいという強い想いがメンバー全員にありました。そこで、通常はデータを固定してから数日かかる臨床試験の解析結果を当日中に出すという目標に挑戦しました。この解析結果は申請時に必要となるもの。ただ急ぐだけでなく、品質も担保しないといけません。両立のためにどう進めるのがベストか考え抜き、外部委託先と社内メンバーが一体となって新しい体制を作ることになりました。
具体的には、普段は外部委託している解析業務の一部を社内で実施し、解析結果の品質チェックを社内メンバーで分担することにしました。タイトなスケジュールだったため,外部委託先だけでは物理的に対応が難しい部分を、社内メンバーが積極的に担当しました。このプロジェクトに直接関わっていない社員の方々からも「できることは手伝います」と声をかけていただき、本当にありがたかったですね。文字通り「塩野義製薬一丸」となって取り組みました。
解析結果が届いたのは、ちょうどプロジェクトの統計解析メンバーとオンラインで打合せをしていたときで、一緒に解析結果を確認しました。プロジェクトを左右する重要な解析結果を前に、「新薬開発の成否に関わる重要な仕事だ」と改めて胸が高鳴ったのを覚えています。
「もう1回」飽くなき挑戦の果てに掴んだ勝利

ーLong COVID(コロナ後遺症)についての解析が特に困難だったとか。
当時は、Long COVIDの定義が明確に定まっていませんでした。どういう症状が、どのくらい続けば後遺症と言えるのか。ブレインフォグと呼ばれる集中力低下や、不眠など様々な症状がある中で、どれを評価の対象とすべきか。手探りの連続でした。
その中で特筆すべきは、無作為化比較試験の中で取得したデータを私たちが扱ったという点です。後遺症のデータと言えば、当時は後ろ向き研究のデータが主流の中で、無作為化比較試験という前向きな研究で取得したデータは本当に貴重なもの。必ず何か意味のある発見ができるはずだ、との想いで取り組み続けました。
大量のデータの中から解析の切り口を検討するのは、まさに霧の中で光を探すような作業でした。しかし、この薬が後遺症に困っている患者さまの役に立つかもしれないと思うと、もう1回、もう1回と挑戦する気持ちが湧いてきました。チーム一丸となったその努力が実を結び、後遺症に関する解析結果について、論文化や国際学会で発表することができました。
「あなたがいる塩野義製薬」の言葉を胸に

ー塩野義製薬の社風について、印象的なことを教えてください。
ーこれからのビジョンを教えてください。
入社間もない頃、上司からかけられた「『T.I.さんがいる塩野義製薬』と言われることを目指してほしい」という言葉。これは、塩野義製薬というブランドの中の一社員ではなく、「私がいるから、塩野義製薬はすごいんだ」と言われるような存在になってほしい、という期待を込めた言葉と解釈しています。この言葉は今も胸に刻まれています。
今、私は、他分野で使われているような統計解析手法を医薬品開発に応用できないか、という観点で研究を進めています。社内のプロジェクトで頼られる存在であることはもちろん、論文や学会発表などを通じて外部でも活躍できる統計家になること。それが私の目標です。