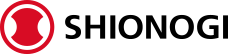AIとデータ分析のスキルを武器に、データサイエンスでヘルスケアイノベーションを加速
2025年1月20日公開
心拍や脳波のデータに秘められた可能性を追求した情報学研究の日々を経て、データサイエンスで医療の未来を切り拓く研究者へ。塩野義製薬のデータサイエンス部で活躍するH.I.さんは、AIとデータ分析のスキルを武器に、創薬研究の革新に挑戦し続けています。
実験効率化からメンタルヘルスケアの新規事業まで、その活動領域は多岐にわたり、わずか入社3年目で特許出願・論文化という成果も達成。研究者の探究心とビジネスの視点を併せ持つ、新時代のデータサイエンティストとして、医療とデジタルの融合がもたらす可能性に果敢に挑む若手社員の姿に迫ります。
.jpg)
好奇心に導かれ、データ×医療の最前線へ
―データサイエンティストとして、製薬業界を選んだのはなぜですか。
―現在のお仕事について教えてください。
大きく分けると2つの柱があります。1つは創薬研究においてのDXを通じた効率化・迅速化です。例えば、これまで、研究者が目視で行っていた動物実験における観察・記録作業を、カメラで撮影してAIで解析し、省力化するといったことです。これにより、研究者はより本質的な研究に多くの時間を使えるようになります。
もう1つがヘルスケア関連の新規事業開発です。特に、ウェアラブルデバイスを使って心拍や睡眠などのデータを取得し、分析してメンタルヘルスケアに活用する取り組みを進めています。弊社はうつ病治療薬の開発で実績がありますが、それに加えて「発症前からの予防」という新たなアプローチでメンタルヘルス分野に貢献したいと考えています。
テクノロジーが変える新しいメンタルケア
.jpg)
―入社後、最初に担当した大きなプロジェクトについて教えてください。
―難しかった点はどのようなところですか。
人間のデータは、個性や個人差も大きく影響するので非常に複雑です。どう解釈すればよいのか迷うことも多く、なかなか結果が見えにくくて、時間だけが過ぎていくこともありました。それでも、今のグローバルな時代では、世界中で行われている製薬研究のスピードが非常に速いため、立ち止まっている余裕はありません。「これでやってみよう」という迅速な判断と、「もう1歩先まで頑張るぞ」という粘り強さの両輪で、諦めずにデータと向き合い続けることで、最終的に成果に結びつけることができました。
また、知財化と論文化も初めての経験でした。特許申請では、知的財産部と協議を重ね、この技術がどのような価値をもつのか、応用することでどういったビジネスプランが考えられるのかビジネス展開まで含めて細部を詰めていきました。論文の執筆では、上司や先輩方に助けていただきながら、こちらも何とかやり遂げることができました。
―現在はどのような段階なのでしょうか。
研究×ビジネスの新しい価値創造
.jpg)
―データサイエンス部の面白さはどんなところにありますか?
研究開発もできるし、ビジネスの観点も学べる「半分研究者、半分ビジネスパーソン」という立ち位置が非常に面白いんです。私自身、入社当初は研究に視点が偏りがちでした。しかし、特に知財化の仕事を通じて、「この特許を取ることで、研究にどういう価値が生まれるのか」「どういったビジネスにつなげていくのか」といったビジネス視点の重要性に気づかされました。
面白い技術や研究成果が出ても、やはりそれだけでは十分ではない。企業として取り組む以上、採算性や市場価値も考える必要があります。知財部門や事業部門など、様々な専門部署と議論しながら形にしていくのは新鮮で楽しいですね。
―その中で、自身の役割をどのように考えていますか。
業界全体のイノベーションを見据えて未来へ
.jpg)
―今後チャレンジしたいことを教えてください。
創薬研究のDXについて、もっと革新的な取り組みをしていければと思っています。今は個別の実験の効率化という形で成果を出していますが、創薬のスピードをガラッと変えられるような、もっと大きなイノベーションを起こしたいです。
新型コロナウイルスの例を引き合いに出すまでもなく、薬を少しでも早く患者さまに届けることは本当に重要な課題であると、世界中で認識されています。将来的には、塩野義製薬だけでなく、製薬業界全体を巻き込んだ研究開発の効率化ができたらと考えています。各社の強みを活かしながら、デジタルやAIの力で、業界全体のスピードアップに貢献できるような研究を立ち上げられたら面白いですよね。
―塩野義製薬の魅力をどのように感じていますか。
誠実な人が多く、仕事がしやすいです。上司も先輩も、若手の意見にしっかりと耳を傾けてくれるので、やりがいを感じています。また、個人の興味や専門性を活かせる環境が整っていることも魅力ですね。データサイエンス部は2021年に設立された若い組織ですが、だからこそチャレンジできる領域が広いと感じています。
その恵まれた環境の中で、今は与えられたテーマに取り組む立場ですが、将来的には自分で研究テーマを見つけて、それをリードしていける存在になりたいと考えています。
.jpg)