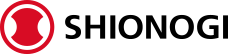医薬の未来はヘルスケアソリューションの中に。新しい営業のカタチをつくる
「患者さまや地域の皆さまに向き合い、地域医療の最適化に貢献することが、これからの製薬会社には必要だと考えています」
塩野義製薬の第一営業部長、山崎哲弘さんは、これまでの枠にとらわれない新しい医薬営業の在り方に挑戦しています。担当エリア全体で、地域ごとに異なる医療環境や顧客ニーズが存在し、それぞれに最適な支援を提供することが大切だと感じています。
こうした多様な医療環境や顧客ニーズに応えるため、SHIONOGIでは医薬品提供に加え、感染症対策を含む全方位型のヘルスケアソリューションの実現に向けた取り組みも進めています。
山崎さんは、医薬品の提供にとどまらず、地域の文化や特性を踏まえた多角的なヘルスケアソリューションの形を模索しています。医療従事者や地域社会との連携を強化し、伝統と革新が融合した新たな医療環境の構築を目指す取り組みは、製薬企業としての挑戦そのものです。

地域特性から見えてきた、新しい営業のカタチ
――第一営業部の概要と地域的な特徴を教えてください。
第一営業部がカバーするのは、北海道から東北、北関東、甲信越までの1道12県。国土の半分以上を占める広大なエリアです。MR(医薬情報担当者)約100名で、約2,500万人の医療ニーズに応える役割を担っています。
人口密度が低く、満員電車での通勤も少ないため、感染症の広がり方も都市部とは大きく異なります。また人口が分散していることで、医療機関までの距離が遠いエリアも多く、受診のタイミングを逃してしまうケースも散見されます。一方で、東北各県をはじめ多くのエリアでは、夏祭りや花火シーズンに外国人も含めた人の往来が集中するため、その時期の感染症対策も非常に重要です。
――そうした地域特性にどのように対応していますか。
地域と共に健康と伝統を守る「東北夏祭りプロジェクト」

――夏祭りでの取り組みについて、具体的に教えてください。
――反応はいかがでしたか。
正直なところ、最初は製薬会社からの提案ということで、やや構えられたこともありました。しかし、「健康を守ることで地域の伝統を守りたい」という想いをお伝えすると、快く協力していただけました。絶やしたくない伝統であり、また観光収入や地域経済にも大きな影響があるからこそ、安全に開催できる環境づくりが重要なのです。
医療は地域の文化や生活と切り離すことはできません。感染拡大予防と治療率の向上のためには、医療機関での活動だけでなく、地域に根ざした活動が必要だと実感しています。
そのため、医療従事者への情報提供だけでなく、地域の文化や生活様式を理解した上で、より包括的なヘルスケアソリューションを提供していくことが、私たちの目指す在り方です。
経済的負担が治療の大きな障壁に
――感染症治療においては、経済的な負担も問題となっています。
新型コロナウイルスの治療薬は、一刻も早く開発するために、製薬会社は人や資金などのリソースを集中して投下しました。新薬には投下した費用を含めて価格を設定されますので、価格が低くなってしまうと開発にかかった費用が回収できず、ビジネスとして成り立たなくなります。そのため、一見、高価な価格に設定されています。
2024年4月以後は、コロナ治療薬の公費支援はないため、患者さまには大きな自己負担が求められ、これが治療を受ける上での患者様の大きな障壁となっています。実際、医師がコロナ治療薬による治療が必要と判断し、患者さまもコロナ治療薬の処方を希望していても、自己負担額が大きいことから治療を躊躇する方も少なくありません。
――こうした課題に対応するため、2025年1月よりPayPayほけんの新たな保険サービス「コロナ治療薬お見舞い金」に協賛しているのですか?
実は、「保険でコロナ治療薬の自己負担を軽減する」というのは、前任である新規事業推進部長時代に自ら提案し、交渉してきたプロジェクトです。当時からコロナ治療薬の薬価はどれも非常に高価であるため、将来的にはこの薬価が「治療率の低下」を招くことが想像できました。そして、新型コロナウイルス感染症で苦しむ患者さまに必要な時に許容できる負担で治療薬が届けられる環境を創りたいと考えていました。今思えば、営業の最前線を離れたからこそ将来の潜在的な問題を俯瞰してみることが出来たのかもしれません。プロジェクトの最初はまさに徒手空拳で、PayPayの「お客様サービスセンター」に電話をかけるところからスタートしました。交渉には苦労しましたが、熱意をもって何度もお話するうちに、PayPay保険サービス株式会社や住友生命保険相互会社のご担当の方々が「重要な社会課題に一緒に取り組みたい」と協力してくださるなど、徐々に賛同者が増え、関係各社の方々との本格的な協議にこぎつけました。
医薬品の提供にとどまらず、経済的負担を軽減する仕組みは、持続可能な社会づくりにとっても重要です。今回の保険サービスのような仕組みは、治療費の負担に苦しむ方々への支援として、そしてサステイナブルな医療環境の実現に向けた大切な取り組みであるといえます。
ヘルスケアソリューションを生み出すHaaS営業

――「HaaS営業組織」という目標を掲げています。
HaaS(Healthcare as a Service)は、医薬品や製品・サービスを包括的に組み合わせたヘルスケアソリューションを提供することです。例えば、感染症の流行予測を天気予報のようにわかりやすくお伝えし、皆さまの日々の健康管理に活かしていただけるような仕組みを検討するなど、柔軟な発想と挑戦の精神を持って未来を見据えています。こういった取り組みをどんどん活発化させるためにも、患者さまや医療現場のニーズを理解し、医薬品とそれに連動する各種製品・サービスを一体的に提供できる体制の強化に努め、お客様目線での価値創造を目指しています。
また、第一営業部としても、医療機関だけでなく、様々なステークホルダーと関係を築いていきたいと考えています。例えば教育委員会やスポーツチームなど、地域に根付いた組織とつながることで、予防医療の観点からも活動の幅を広げていきたいと考えています。
――最後に、第一営業部の目指す姿を教えてください。